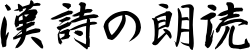秦淮に泊す 杜牧(しんわいにはくす とぼく)
■【中国語つき】漢詩の朗読を聴く
■【古典・歴史】メールマガジン
YOUTUBEで配信中
▼音声が再生されます▼
泊秦淮 杜牧
煙籠寒水月籠沙
夜泊秦淮近酒家
商女不知亡國恨
隔江猶唱後庭花
秦淮(しんわい)に泊(はく)す 杜牧(とぼく)
煙(けむり)は寒水(かんすい)を籠(こ)め 月(つき)は沙(すな)を籠(こ)む
夜(よる) 秦淮(しんわい)に泊(はく)して 酒家(しゅか)に近(ちか)し
商女(しょうじょ)は知(し)らず 亡国(ぼうこく)の恨(うら)みを
江(こう)を隔(へだ)てて猶(なお)唱(とな)う 「後庭花」(こうていか)
現代語訳
寒々した冬の秦淮河にもやが立ちこめ、
砂地を包み込むように月光が照らしている。
夜、秦淮河のほとりに泊まった。居酒屋が立ち並ぶあたりだ。
酒場の歌い女たちは知るまい。陳の後主陳淑宝が酒びたりでついに国を滅ぼしてしまった、その痛ましい話などは。
河の対岸では、いまだにその「玉樹後庭花」の歌を歌っている。
語句
■秦淮河 秦代に開かれた運河。江蘇省句容県(くようけん)の北、および溧水県(りっすいけん)の東南からはじまり、南京市内に入り、長江に注ぐ。現在も秦淮河の沿岸は繁華街。 ■煙籠寒水 夜霧が秦淮河の冷たい水の上に立ち込めているようす。 ■月籠沙 月の光が地面に落ちて白砂と区別なつかないようす。 ■商女 酒をすすめ歌舞を披露する女。 ■亡國恨 贅沢三昧で国を滅ぼした陳の後主(陳淑宝)の怨み。 ■後庭花 「玉樹後庭花」という曲名の略。作者は陳の後主(陳淑宝)。六朝最後の皇帝。酒食にふけり国防を顧みなかったため、陳は隋にほろぼされた。
解説
【秦淮河】は南京城内を流れる河です。その両岸には居酒屋が立ち並んでいました。そこの歌い女たちが、意味もわからずに歌を歌っているのです。
【玉樹後庭花】南北朝時代の陳の国王陳淑宝の歌です。この国王は国防には興味が無く、詩歌や芸術、そして酒と美しい女性を愛しました。
国王が酒びたり女びたりとなれば国が乱れます。ついに隋の軍隊が攻め込んできて、陳は滅亡しました。南朝六代の栄華も絶えたのでした。
そういう、痛ましい歌の由来を思うと、作者はとても心が痛むのです。でも歌い女たちはそんな由来なんて詳しくは知らず、ノリだけで歌ってるンだろうなあ…と。
舟旅の途中、一泊するというのは、漢詩でよく扱われる主題です。張継「楓橋夜泊」、孟浩然「建徳江に宿す」、頼山陽「天草洋に泊す」など。
次の漢詩「揚州の韓綽判官に寄す」