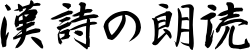登岳陽楼 杜甫(がくようろうにのぼる とほ)
■【中国語つき】漢詩の朗読を聴く
■【古典・歴史】メールマガジン
YOUTUBEで配信中
↓↓↓音声が再生されます↓↓
http://roudoku-data.sakura.ne.jp/mailvoice/Gakuyourou2.mp3
登岳陽楼 杜甫
昔聞洞庭水
今登岳陽楼
呉楚東南坼
乾坤日夜浮
親朋無一字
老病有孤舟
戎馬關山北
憑軒涕泗流
岳陽楼(がくようろう)に登る 杜甫
昔聞く洞庭(どうてい)の水、
今登る岳陽楼。
呉楚(ごそ)東南に坼け、
乾坤(けんこん)日夜浮かぶ。
親朋(しんぽう)一字無く、
老病(ろうびょう)孤舟(こしゅう)あり。
戎馬(じゅうば)関山(かんざん)の北、
軒(けん)に憑(よ)れば涕泗(ていし)流る。

夔州から岳州へ
現代語訳
かねて噂に聞いていた洞庭湖を訪れ、そのほとりの岳陽楼に登る。
呉楚の東南の地方が二つに裂けたという洞庭湖には、宇宙のすべてが一日中浮かんでいるようだ。
手紙をくれるような親類も友達もなく、老いて病持ちの私には持ち物といっても小舟が一双あるだけだ。
関山の北ではまだ今も戦が続いているという。
楼のてすりに寄りかかっていると、涙が流れてくる。
語句
■岳陽楼 洞庭湖の東北端。岳州県城西門の楼。洞庭湖を見下ろし風光明美。 ■洞庭水 湖南省北部の中国第二の湖(第一は青海湖)。■呉楚 春秋時代の国の名前。「呉」は現在の江蘇・浙江省、「楚」は湖北・湖南省。その東南部分が裂けて洞庭湖ができたという。 ■乾坤 天地。 ■親朋 親類や友達。 ■無一字 一字の便りも無い。 ■老病 老いて病気がちの我が身。 ■孤舟 ただ一双の舟。柳宗元「江雪」に「孤舟蓑笠翁」とある。 ■戎馬 軍馬。戦争のこと。 ■関山 関所や山。 ■軒 手すり。欄干。 ■涕泗 涙。
解説
大暦3年(768年)、杜甫57歳の作。杜甫が二年間滞在した夔州(四川省奉節県)を出発し、長安を目指していた途中立ち寄った岳州(湖南省岳陽県)での経験を詠んだ詩です。

夔州から岳州へ
洞庭湖は湖南省北東部の景勝で、いろいろな詩に詠まれています。岳陽楼は洞庭湖の東岸、岳陽城の正門に建つ三層の楼台です、洞庭湖を見下ろします。
孟浩然の「洞庭湖を望んで張丞相に贈る」と杜甫のこの「登岳陽楼」が、洞庭湖をうたった詩の双璧とされます。
前半は洞庭湖の壮大なながめ。後半は大自然の中にあって、みじめな己の姿と孤独な心中を描きます。それでも杜甫の詩は個人的な内面描写にとどまらず、最後には天下国家のこと、戦争が続いているという話につながっていきます。
すでに安史の乱は終結(763)していますが、各地で小規模な反乱が続いていました。そして、この年の8月、吐蕃(とばん、チベット)が長安の西、鳳翔(ほうしょう)に攻め入ってきます。
この2年後、杜甫は洞庭のあたりを放浪し、ふたたび岳州へ向かう途中、亡くなりました。、舟の上で死んだというのは一つの伝説です。
松尾芭蕉は『おくのほそ道』の冒頭に杜甫を念頭に置いてこう書いています。
月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也。舟の上に生涯をうかべ、馬の口とらえて老をむかふる物は、日々旅にして旅を栖とす。
「舟の上に生涯をうかべ」の一節は、旅の途上、舟の上で死んだといわれる杜甫を念頭に置いていると思われます。同じく『おくのほそ道』松島の章では、
仰(そもそも)ことふりにたれど、松島は扶桑第一の好風にして、凡(およそ)洞庭・西湖を恥ず。東南より海を入て、江の中三里、浙江の潮(うしお)をたゝふ。
松島の景観を洞庭湖になぞらえます。
また『幻住庵の記』では、滋賀県大津市の国分山から見下ろす琵琶湖の景色を、杜甫の「岳陽楼に登る」を引用しながら、洞庭湖になぞらえます。
魂、呉・楚東南に走り、身は瀟湘・洞庭に立つ。山は未申にそばだち、人家よきほどに隔たり、南薫(なんくん)峰よりおろし、北風湖(うみ)を浸して涼し。
杜甫を出発点として芭蕉に踏み込んでいく。あるいは芭蕉をきっかけとして杜甫の詩を読んでみるのも、楽しいと思います。
現代語訳
八月の洞庭湖の水はまっ平らで、
大空をひたして水と天が溶け合っているようだ。
雲夢の沢で水蒸気が蒸し、
波は岳陽城の城郭をゆるがしている。
この水を渡ろうとするも舟もかじも無く、
この聖明の世に無為徒食の自分の身を恥じ、じっと座っている。
ぼんやりと釣り人を眺めていると、
こんな私でも魚を釣りたい気持が起こってくる
次の漢詩「江南にて李亀年に逢う」